「どうして話さないの?」
「家ではあんなに元気なのに、学校だと別人みたい…」
そんな風に感じたことはありませんか?
私の娘が「場面緘黙症」と医師から診断されたのは、保育園の年少組のときでした。家庭ではおしゃべりなのに、外では一言も話さない。その違いに戸惑いながらも、少しずつ理解し、親としてできることを模索してきました。
今では、おとなしいながらもクラスで少し話せるようになり、子どもの成長を日々感じています。
この記事では、同じように悩むママやパパに向けて、わが家で実際にやってよかったこと、園や学校とのやりとり、親自身の心のケアまでお伝えします。
「話さないのはなぜ?」場面緘黙症の基礎知識

場面緘黙症ってなに?よくある誤解も
場面緘黙症とは、ある特定の場面で話すことができなくなる不安障害の一つ。例えば、家庭では普通に会話できるのに、学校や園などの場では声が出なくなってしまいます。
周囲からは「無口」「恥ずかしがり屋」「しつけの問題」などと誤解されがちですが、本人の意思で黙っているわけではなく、「話したくても声が出ない」状態なのです。
私も最初は「人見知りかな?」と軽く考えていたのですが、実際には本人にとっては強い不安があって、思うように動けない状況だったのだとあとから知りました。
うちの子に限って…?発症のきっかけはいろいろ
場面緘黙症のきっかけは子どもによってさまざまです。例えば、環境の変化、人前に出ることへの強い不安、繊細な気質などが関係すると言われています。
わが家の場合は、引っ越しにともなう保育園の転園が大きかったと思います。それまでは慣れた環境で元気に過ごしていたのに、新しい保育園では一言も話せなくなりました。
はじめは「そのうち慣れるよね」と思っていたのですが、日が経っても変化がなく、不安になって受診したところ「場面緘黙症」と診断されました。
恥ずかしがり屋とはちがうの?
場面緘黙症は、単なる人見知りやシャイとは違います。恥ずかしがっているのではなく、心と体が「話せない状態」になっているという点が大きなポイント。
その違いを理解してもらうまでが、周囲への説明の難しさでもありました。でも、理解が広がるほど、子ども自身が過ごしやすくなるので、まずは親が正しく知ることが大切だと思います。
親にできること、実際にやってみてよかったこと

まずは安心がいちばん。話すことは無理に求めなくてOK
娘が話さない姿を見て、つい「ほら、先生にごあいさつは?」「ちゃんと返事しなきゃダメよ」なんて言ってしまったことがありました。でもそれは、プレッシャーになっていたんですよね。
「話さなくても大丈夫」「ここでは安心していていいんだよ」と伝えることで、少しずつ表情が柔らかくなっていきました。
親としては不安になりますが、焦らず「話さなくても存在を認められる」経験を積み重ねることが、結果的に回復の近道だったと感じます。
言葉がなくても伝わる!ジェスチャーや表情も立派な会話
声が出ない時期は「うなずく」「指差す」「カードを使う」などで気持ちを伝える練習をしました。
先生にもその方法を共有し、「声が出なくても気持ちが伝わる」環境を整えることで、少しずつコミュニケーションへの不安が和らいでいったように思います。
「できた!」を少しずつ。成功体験が自信につながる
小さなステップでも、成功体験をしっかり認めてあげることはとても大事です。
ある日、「今日ね、先生と目が合ったらニコッてできたんだ」と本人が教えてくれたことがありました。声が出なくても、「あいさつの代わりに笑顔で反応できた」というその経験は、本人にとって大きな一歩。
「すごいね」「よかったね」と心から喜ぶことで、自信がつき、次の行動につながっていきました。その積み重ねのおかげか、今では学校でも少しずつ自分から話せるようになり、笑顔で帰ってくる日が増えました。
親もつい焦っちゃうけど…その子のペースを大事に
正直、私は何度も焦りました。周りの子が普通に発表していたり、お友達と楽しそうに話している姿を見ると、「なんでうちの子だけ…」と落ち込んでしまうこともありました。
でも、場面緘黙症は「その子なりのペース」が本当に大事。あせらず、比べず、少しずつ、が一番の近道でした。むしろ、子どもから教えられることのほうが多かった気がします。
学校や先生とのやりとり、こんな風にしてます
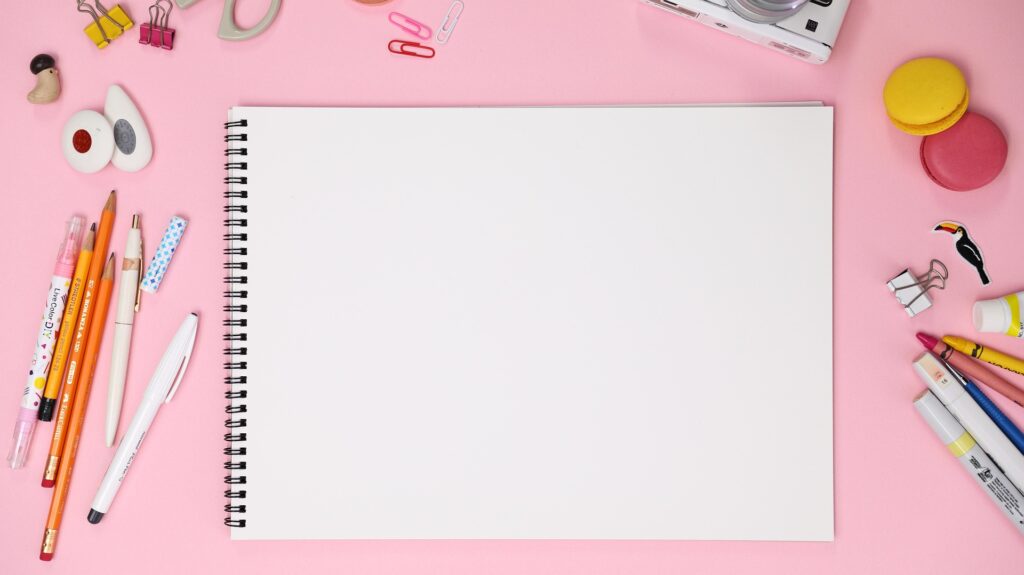
最初の一歩は「伝えること」から
最初は、先生にどう伝えたらいいか迷いました。でも、担任の先生に率直に「家では話すけれど、保育園では声が出ないようです」と話したところ、とても理解を示してくださってホッとしたのを覚えています。
伝えることで、園や学校側も配慮しやすくなります。あのとき、勇気を出して相談して本当によかったです。
うちで使ったサポートメモ、こんな内容でした
我が家では、先生との連携をスムーズにするために、A4用紙1枚程度の「サポートメモ」を渡しました。内容は以下のようなことです。
・家ではよく話しますが、園では緊張して声が出にくいようです
・声が出ないときは、ジェスチャーや表情で反応します
・無理に発言を求められると、余計に固まってしまうことがあります
・見守ってもらえるだけで安心できるようです
こうしたメモがあると、先生も配慮しやすく、対応が安定してきました。
「配慮してほしいこと」を具体的に伝えるコツ
お願いごとは、なるべく「こうしてもらえると助かります」といった形で伝えるのがおすすめです。
「返事ができないときは、にっこり笑うだけでOKにしてもらえますか?」
「人数の少ないグループ活動のほうが安心できるようです」
具体的に伝えることで、先生も日々のなかで無理なくサポートできる環境を作ってくれました。
ひとりで抱えないで。相談できる場所もあります
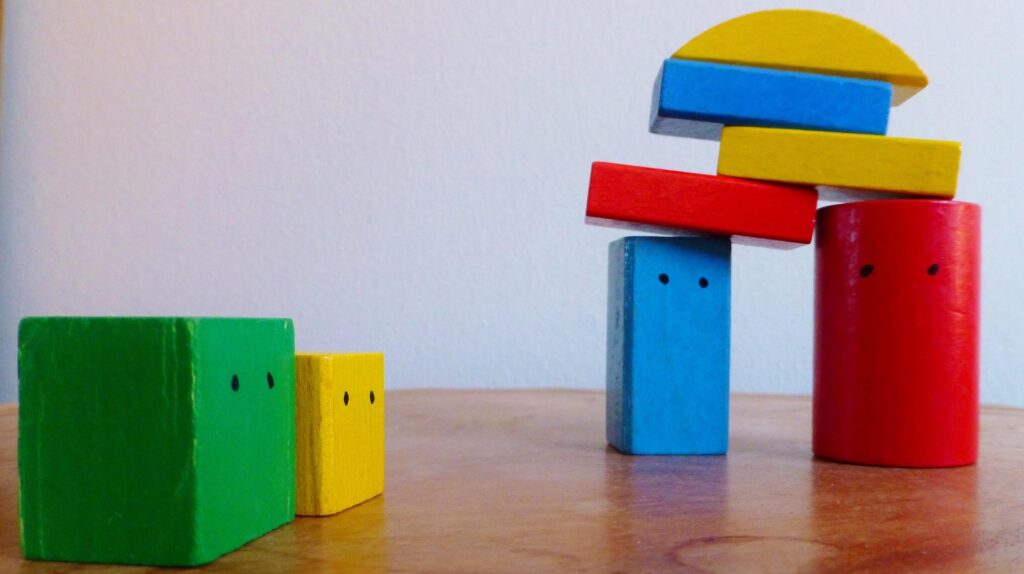
どこに相談したらいい?頼れる機関や窓口
場面緘黙症に詳しい支援機関や医療機関は意外と多くあります。以下のようなところに相談してみるとよいかもしれません(各機関の名称は自治体によって異なります)。
・発達相談センター
・子ども家庭支援センター
・児童精神科・小児科
・保健センターの子育て相談 など
いきなり受診が難しい場合は、学校のスクールカウンセラーなどに相談してもOK。今は支援体制が整いつつある時代なので、早めに動くことで選択肢が広がります。
療育やカウンセリングって実際どう?
わが家の場合は、児童発達支援の療育には通いませんでしたが、自治体が行っている臨床心理士による親子カウンセリングに数回通いました。
子どもにとっても安心できる場所だったようで、少しずつ緊張がやわらぐ様子が見られました。そして何より、私自身が話を聞いてもらえる時間を持てたことで、「大丈夫、見守っていこう」と思えるようになったのが大きかったです。
費用も無料で、気軽に相談できる体制だったので、「とりあえず行ってみよう」くらいの気持ちで動いてみるのもおすすめです。
親だってしんどいときがある。そんなときは
正直、私も何度も悩みました。周りの子が楽しそうに話す姿を見ては「なんでうちの子だけ…」と落ち込んだり、焦ったり、自分を責めたり。
でもそんなとき、私の支えになったのが、自治体の臨床心理士さんによるカウンセリングでした。話を聞いてもらうことで、気持ちが軽くなって、また前を向けるようになりました。
もう一つ、心の支えになったのが、同じような経験をしたママたちのブログです。「うちだけじゃないんだ」「この子にはこの子のペースがあるんだ」と気づかせてくれました。
子どもを支えるには、まず親が元気でいることが大切。もし今つらいと感じているなら、どうかひとりで抱えず、誰かの言葉や手を借りてください。きっと少しずつ、道が見えてくるはずです。
おわりに|少しずつ、一緒に歩いていけたら

場面緘黙症と向き合う毎日は、正直、うまくいかないこともたくさんありますよね。私自身、何度も立ち止まりながらここまで来ました。
それでも、娘のちいさな「できたね」を一つひとつ喜んでいくうちに、少しずつ道がひらけてきたように思います。
今では娘も小学校高学年になり、クラスではおとなしいほうですが、少しずつ自分の言葉で話せるようになってきました。あの頃は「この先どうなるんだろう」と不安でいっぱいでしたが、少しずつでも進んでいる実感があります。
大事なのは、話せないことを無理に変えようとしないこと。そして、「そのままの子ども」を見つめながら寄り添っていくこと。
あせらなくて大丈夫。子どもにも親にも、それぞれのペースがあります。
これからも、できることを一歩ずつ。そんなふうに、一緒に歩いていけたら嬉しいです。
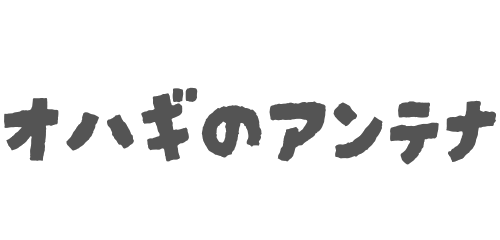
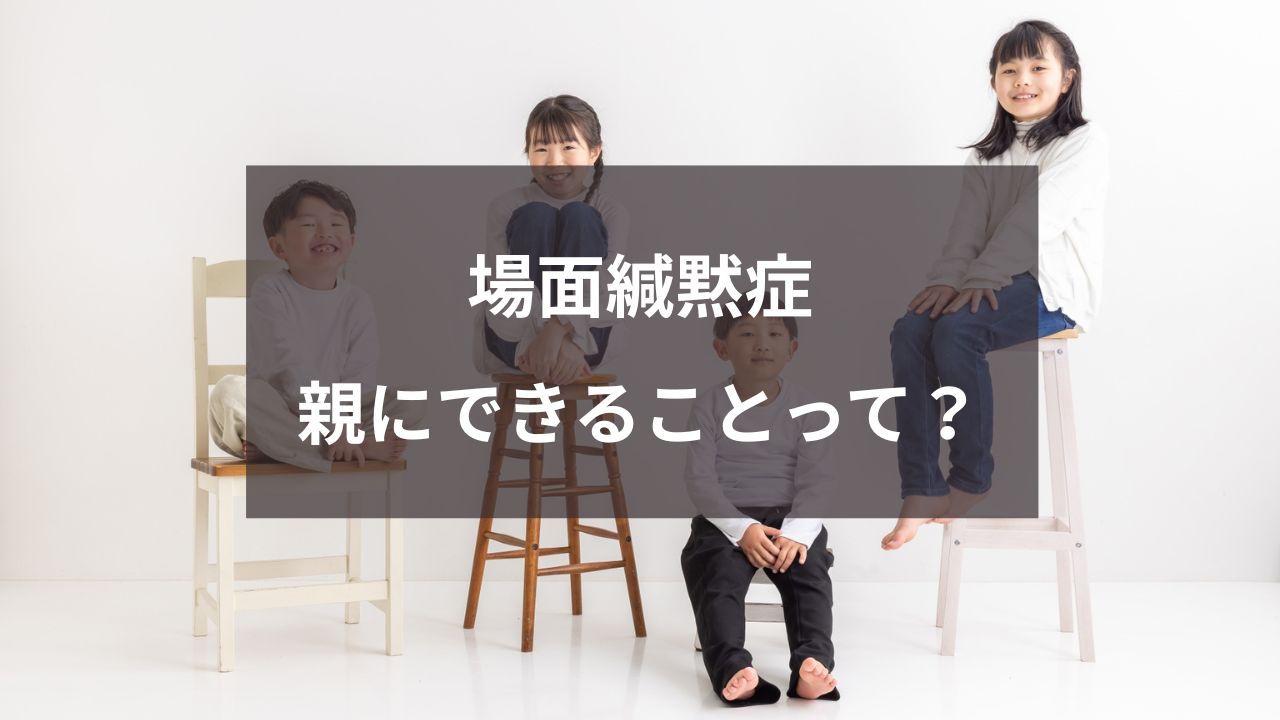
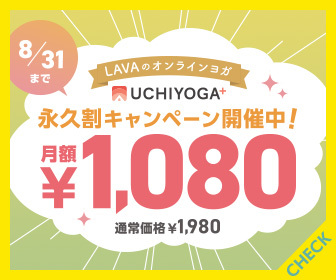
コメント